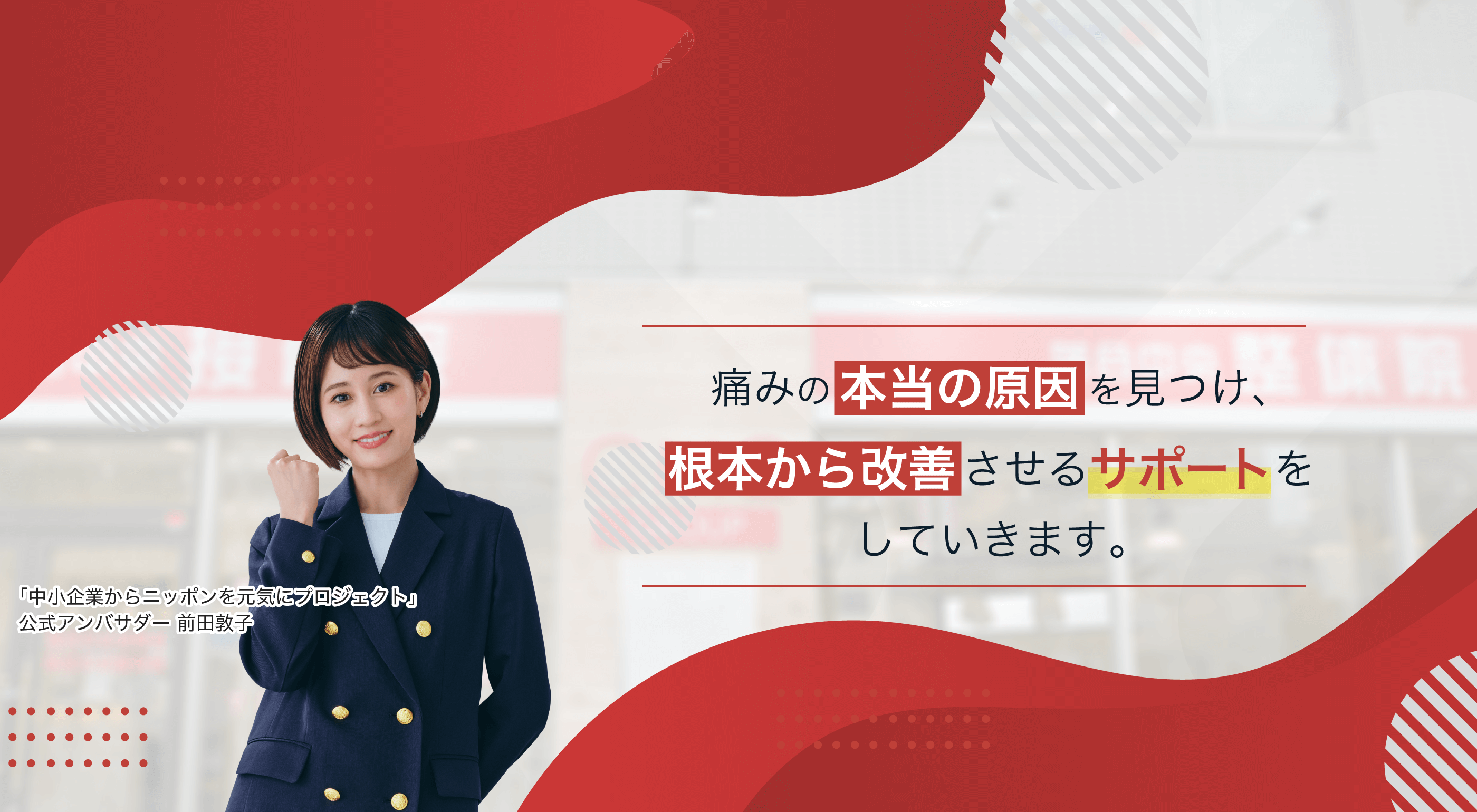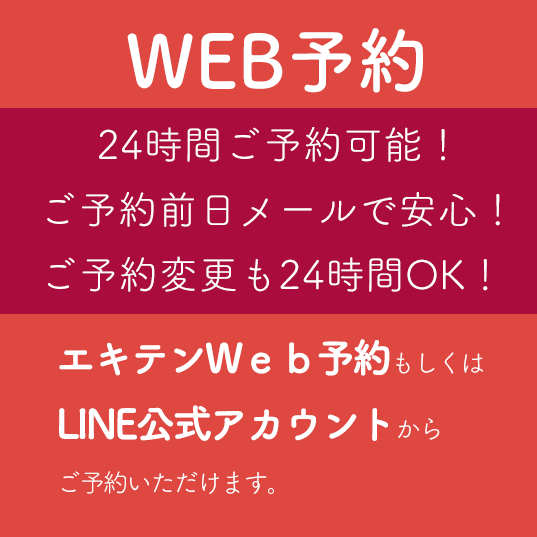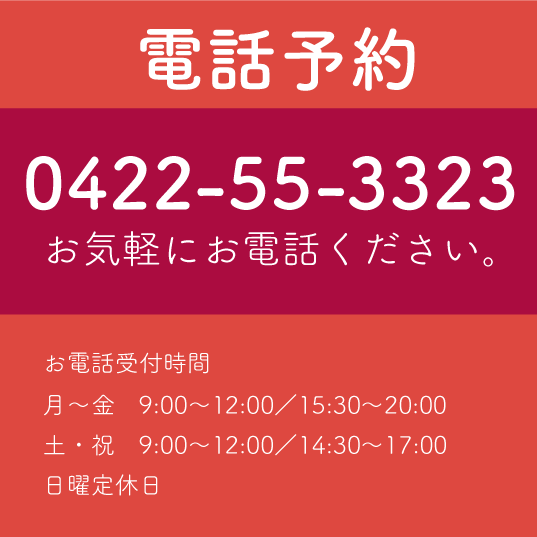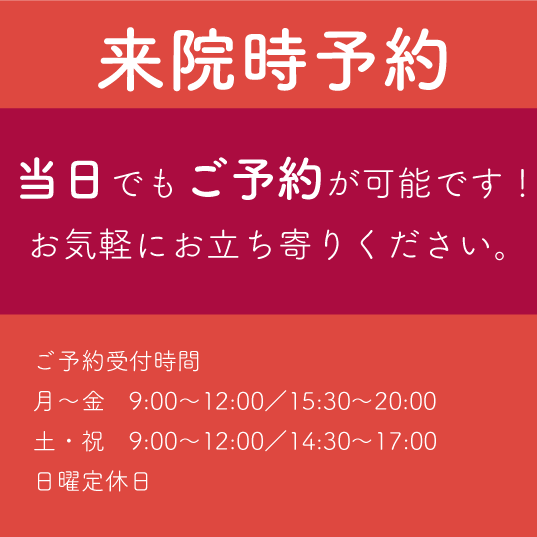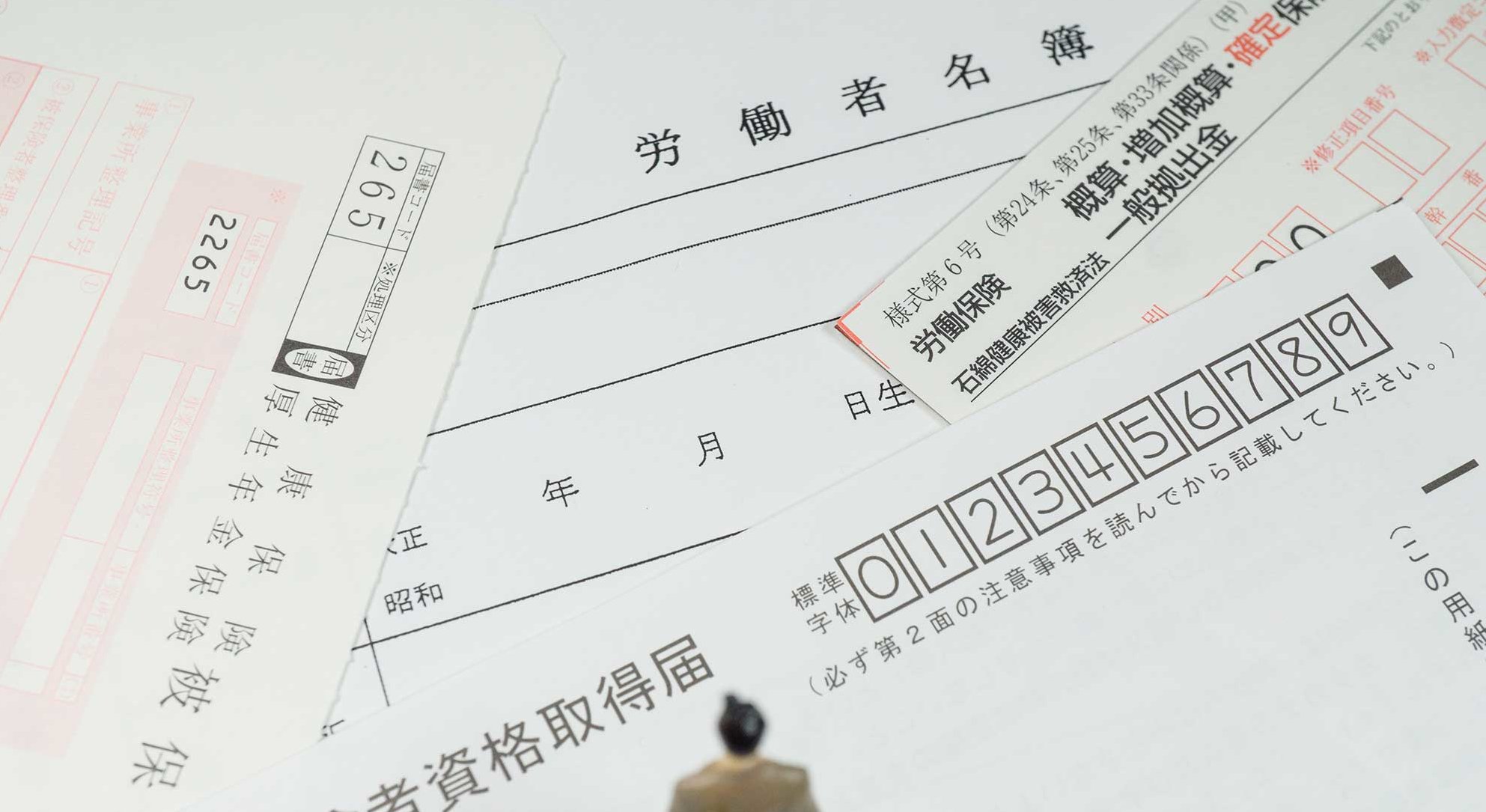痛みで困ってる人を助けたい !
ケガの早期回復、腰痛や肩のつらさ、
産後の女性の身体の不調などをこの手で改善へ導きます。
世界中の人達の健康寿命を伸ばす為に。スタッフ一同全力尽くします。
武蔵境中央整骨院からのお知らせ News
-
- 2024.4.01 ニュース 【4月】受付時間変更のお知らせ
経営方針発表会に参加するため受付時間を変更させていただきます。
ご不便、ご迷惑をお掛けしますがご了承の程、宜しくお願い申しあげます。<受付時間変更のお知らせ>
4/13(土) 午前は通常通り9:00~12:00受付、午後は経営方針発表会参加のため休み
以上です。
-
- 2024.4.01 ニュース 肩こりを本気で治すならインナーユニット?!
首や肩、背中がこっているときはどのように対処されていますか?
多くの場合、こっている部分を叩いてもらったり、揉んだりするのではないかと思います。
そうすると確かに楽になるのですが、しばらくするとまた戻ってしまいませんか?実は首や肩、背中のこりは、過度な緊張や血行不良により僧帽筋にあらわれた“症状”であって、真の原因はほかにあるのです!
そのため、こったところを揉むだけで原因の改善にアプローチしないと、元に戻ってしまうのです(>_<)その原因となるものがインナーユニットです。
インナーユニットは、腹腔を覆っている4つのインナーマッスル(深層筋)です。
体幹にあるここが緩んでしまうと、身体は動作のために首や肩の筋肉まで動員して「代償運動」をするようになり、僧帽筋や肩甲挙筋などにストレスがかかります。インナーマッスルを具体的に挙げますと、
・横隔膜(おうかくまく)
・腹横筋(ふくおうきん)
・多裂筋(たれつきん)
・骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)
です。そして、次の役割があります。
・姿勢の安定
・体幹の安定
・内臓の保護
・動作の補助肩こりを根本的に改善するためには、肩だけではなく、姿勢を整えてインナーユニットを鍛えましょう(^^♪
このインナーユニットにアプローチするストレッチを説明したYouTube動画があります。
『腰痛も肩こりも2つのストレッチでマルっと解決!インナーマッスルストレッチ』
ご興味のある方はぜひご覧ください(^^♪チャンネル登録もお願いします☆
-
- 2024.3.01 ニュース そのギックリ腰の原因はインナーユニットかも?!
春の陽気かと思えば真冬の寒さになったりと今年は寒暖差が激しいですね(>_<)
この気候の変化に身体がついていかず、体調を崩される方も多いようです。
ご自愛くださいね。話は変わりますが、インナーユニットをご存じですか?
インナーユニットとは、内臓や骨盤、腰椎などが収められた腹腔をまるでコルセットのように覆っている4つのインナーマッスル(深層筋)です。具体的には、
・横隔膜(おうかくまく)
・腹横筋(ふくおうきん)
・多裂筋(たれつきん)
・骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)
です。身体のあらゆる動作は、はじめにインナーユニットが引き締り手足など必要な筋肉を動かしているので、別名“初動筋”とも呼ばれています。
すべての動きはインナーユニットからはじまるとも言えるのです。そのためインナーユニットが緩んでしまうと、筋肉や関節の動きがチグハグになり、ギックリ腰などのトラブルを引き起こすことも・・・。
その他にも、姿勢の崩れや内臓の機能低下、冷え症などの原因にもなります。このようにインナーユニットはとても大切なのです。
このインナーユニットの解説やセルフトレーニングの方法を説明したYouTube動画があります。
『骨盤底筋を鍛えろ!尿もれにドローイン』
ご興味のある方はぜひご覧ください(^^♪
チャンネル登録もお願いします☆”
-
- 2024.2.01 ニュース お腹まわり冷えていませんか?
今年は暖冬の予報が出ていましたが寒いですね(>_<)
冷えは万病のもとと言ったりもしますので、身体を冷やさないようにお気を付けくださいね。とは言っても、冬ですので体を冷やしがちです。
そして、お腹まわりを冷やしてしまっている方が多くいらっしゃいます。次のようなお悩みはありませんか?
・手足がつる(ときどき)
・お腹が冷える
・お腹が張るこのような方はお腹が冷えている可能性があります。
これを放っておくと、腰痛(垂れ尻)や肩痛(五十肩)、首痛(猫背)などになってしまうことも・・・。そんな方にお勧めの施術がHOT腸もみです。
『HOT腸もみ』は、心地よい熱を身体の深部まで届けられるホットストーンを使用してお腹を温めながらほぐすケアです。
岩盤浴と腸もみとセルライトドレナージュの良いところを組み合わせ、効果を最大限に発揮できるように開発した施術です。今月の健康新聞は、この『HOT腸もみ』についてまとめました。
健康新聞は院内でお配りしていますのでぜひご覧ください(^^♪また、『HOT腸もみ』について解説したYouTube動画があります。
『ホットストーン×腸もみ HOT腸もみ』
ご興味のある方はぜひご覧ください!
ご自宅でできるセルフケアの解説もあります(^^♪チャンネル登録もお願いします☆”
-
- 2024.1.01 ニュース 今年は“天使の羽”で、映える健康♪
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申しあげます。年初のテーマはその形から“天使の羽”と呼ばれることもある肩甲骨です(^^♪
肩甲骨は肩や腕の動きを支える役割とともに、周辺には脂肪を燃焼させる細胞の集中スポットがあることをご存じですか?身体には大きく分けて2種類の脂肪細胞があります。
1つが「白色脂肪細胞」です。
おもにお腹まわりに存在し、余分なエネルギーを脂肪として蓄える性質があり、これが肥満の原因となります。もう1つが「褐色脂肪細胞」です。
脂肪を燃焼して熱をつくる働きがあり、肩甲骨の間などに存在しています。褐色脂肪細胞は、体温調節機能が未熟な赤ちゃんの身体が、体温を維持するために脂肪を燃焼させる細胞です。
年齢とともに消退すると思われてきましたが、成人になっても存在することから、ダイエットへの応用が期待されるようになりました(^^♪
そのため、脂肪を燃焼させるカギは肩甲骨にアリとも言われています。そんな肩甲骨ですが、デスクワークなどで同じ姿勢を続けることにより動きが悪くなっている方が多くみられます。
そのような方にお勧めしたいのが「肩甲骨はがし」です。ただ“はがす”といっても痛みをともなうケアではありません。
やさしい手技などで関節や筋肉の柔軟性を高めていく施術です。
硬くなった肩甲骨に滑らかな動きを与えることで、肩回りの不調の改善が期待できることに加えて、脂肪細胞の活性化も期待できます。
更に、東洋医学では、風邪の原因となる“邪気”は、肩甲骨の間にある“風門”を通って侵入するとされるため、冷え性対策としての効果も期待できます。実際にどのような施術なのかを解説しているYouTube動画があります(^^♪
『痛みが取れる 肩甲骨はがし』
ご興味のある方はぜひご覧ください(^^♪
チャンネル登録もお願いします☆